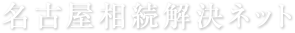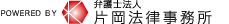遺産分割方法としての換価分割
遺産分割方法としての換価分割
遺産分割の際に、どのような方法で遺産を分割するかについては悩ましい問題です。例えば、遺産の中に建物がある場合、建物そのものが欲しいという人と、建物を売って現金が欲しい人とでは、分割方法に争いが生じ、遺産分割が進みません。
今回は、遺産分割方法の中でも、換価分割、特に競売についてご紹介します。

遺産分割の方法
遺産分割における具体的な分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の4種類があります。
遺産分割の基本原則は現物分割です。しかし、不動産以外に遺産が存在しない場合や、会社の経営権に関わる株式が存在する場合など、現物分割が困難な場合は多くあります。遺産を取得する代わりに代償金を払える場合には代償分割をし、代償分割すら困難な場合には換価分割がなされるべきです。
しかし、上記の優先順位はあくまで一般論です。実務上は、分割方法につき、いずれを選択するかについて、当事者の意向を聴取し、可能な限りこれを尊重する運用をしています。
調停では、ほとんどの場合、当事者が合意すれば、いかなる分割方法を採ることも可能です。
審判でも、当事者の希望がある程度一致している場合は、その希望通りの分割方法が採られることが多いです。
当事者間で、遺産分割方法について争いがある場合、審判になれば、優先順位での遺産分割方法が検討されます。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却等で換価(換価処分)した後に、代金を分配する方法です。任意売却と競売の方法があります。
任意売却
任意売却は、当事者の合意に基づいて、換価代金を分割対象財産とすることを前提として、第三者に売却し、その代金を分配する方法です。対象財産を高額で売却することが期待でき、手続の進行も早いです。
しかし、当事者の合意がなければ、進めることはできません。
なお、家事事件手続法第194条第2項では、家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずることができるとしています。任意売却を命じた際に、その命令に強制力があるのか、強制力があるとしてどのような手続になるのかについては判然としません。
競売
他方、家庭裁判所は、遺産分割の審判をするため、必要があると認められるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売して換価することを命ずることができます(家事事件手続法第194条第1項)。遺産の全部を競売に付す場合は、その換価代金を当事者全員の具体的相続分に応じ分配する旨を定めることになります。
競売手続は、おおむね以下のような流れで行われます。

- 任意売却が可能であるかの相続人に対する意見聴取(家事事件手続法第194条第2項但し書き)
任意売却による換価を行えないかについて、意見聴取をおこないます。 - 財産管理人の選任(家事事件手続法第194条第6項)
審判の効力が発生するまでの間、財産の管理をさせるための財産管理人を選任します。 - 審判の発令(家事事件手続法第194条第1項)
遺産の分割の審判をするため必要があると認められると、競売による換価が命じられます。 - 審判の確定(家事事件手続法第74条第1項、第4項、第86条1項)
審判が告知され、2週間で確定します。 - 競売の申し立て(家事事件手続法規則第103条第2項、民事執行法第195条、第188条、第44条)
換価の実行を命じられた相続人は、執行裁判所に競売を申し立てます。 - 競売開始決定(民事執行法第45条第1項、第2項)。
執行裁判所は、競売が開始の宣言を送達します。 - 執行官による現況調査等(民事執行法第57条、第58条)
執行官による差押不動産の現況調査報告書、評価人による当該不動産の評価書が提出されます。 - 執行裁判所による売却基準額の設定(民事執行法第60条)
評価人の評価に基づき不動産の売却基準額を決定します。 - 売却許可決定(民事執行法第69条)
最も高い価格に入札した者に対し、売却許可決定を行い、決定から1週間で確定します。 - 代金の納付
売却許可決定の確定後から1ヶ月以内の裁判所書記官が定める日までに代金が納付されます。 - 配当
買受人から納付された代金を各相続人に対し審判(配当表)に従って分配します。
このように、競売手続には時間がかかるのが実情です。また、一般的に競売における落札価格は、任意売却における売却価格よりも低くなってしまいます。
そのため、遺産の換価分割を望む相続人の方は、他の相続人の方へ、最終的に競売となってしまうことによる時間的、金銭的不利益を説明した上で、任意売却をする合意をとるようにすべきといえるでしょう。
まとめ
以上の通り、遺産分割の方法の中でも、換価分割について確認しました。
当事務所では、遺産分割に関する紛争について豊富な取扱・解決実績がありますので、お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
(2023年4月24日)
※記事が書かれた時点の法令や判例を前提としています。法令の改廃や判例の変更等により結論が変わる可能性がありますので、実際の事件においては、その都度弁護士にご相談を下さい。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
遺産分割についてさらに詳しく知りたい方はこちら
- 高額な土地がある場合の遺産の分割方法は?
- 愛人の子は遺産を相続できる?
- 遺産分割方法としての換価分割
- 亡くなった父親が再婚していた場合の遺産分割
- 共有物の管理に関する法改正(令和3年の民法改正)
- 遺産分割前に故人の預金を引き出してもいいの?
- 配偶者居住権とは
- 子供のいないご夫婦の相続
- 相続法改正!遺産分割前の預貯金の不正引き出し問題
- 被後見人が囲い込まれている場合の後見申立
- アパート経営者の遺産。賃料はどう扱う?
- 遠隔地で遺産分割調停が申し立てられた場合
- 遺産分割の「前提問題」とは?
- 遺産分割後に遺言が見つかった場合の対応
- 認知症の相続人がいる場合の遺産分割
- 遺産分割協議書のひな形
- 非嫡出子がいる場合の遺産分割
- 未成年者の相続人がいる場合の遺産分割
- 現物分割、代償分割、換価分割のメリット・デメリット
- 面識のない(知らない)相続人がいる場合の遺産分割
- 行方不明の相続人がいる場合、遺産分割はどうすればいいの?
- 生前に引き出された預貯金をめぐる訴訟の問題(引出の権限)
- 遺産分割協議と遺産分割協議書
- 遺産分割調停と審判
- 遺産に関連する訴訟について