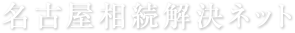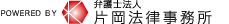相続問題についての知識
生前に引き出された預貯金をめぐる訴訟の問題(引出の権限)
1 生前に引き出された預貯金をめぐる紛争はよくある?
亡くなられた方の預貯金口座を管理していた者が預貯金を勝手に引き出し、多額の預貯金が失われてしまうというのは、よくあることです。 その際、不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求ができることは、既にご説明しました。(預金の使い込みについて)
この問題はよくある問題であるにもかかわらずまとまった書籍などは無く、裁判所の判断はケースバイケースだと言われています。

名古屋地方裁判所では、このような問題について裁判官が研究を行い、一定の知見が得られていますので、今回はこれについてご紹介させて頂こうかと思います。(判例タイムズ1414号p74~)。なお、以下は、同研究結果に対する弊所の解釈をご紹介するものであり、弊所独自の見解も含めた記載となっております。
2 預貯金を引き出す権限はあったのか?
この手の紛争でよく争いになるのは、亡くなられた方から預貯金を払い戻す権限を与えられていたか否か、という点です。 訴えられた側は、自分は亡くなられた方(被相続人)から権限を与えられていた、なので違法なことは何一つしていない、よってお金を返す理由は無い、と争うことになります。
このような権限があったことを原告と被告のどちらが主張立証するべきでしょうか。
もし、原告(訴えた側)が主張立証しなければならないなら、原告は被告(訴えられた側)の無権限を主張立証しなければなりませんが、結構大変そうです。離れて暮らしていたならば尚更です。生活の実情を知りませんから。
他方、被告が主張立証しなければならないと、通常、親密な関係だと書面(たとえば委任状とか)で権限を授与するということはあり得ないですから、権限を与えられたという証明ができず、これもまた大変そうです。
預貯金を引き出す権限があったことを立証すべきなのはどっち?
これについて、裁判官の実感としては、
実際の事件においては、引出権限の存否は殆ど認定ができ、あまり原告被告のどちらが主張立証責任を負担するかで差が無いのではないか、とのことです。
すなわち実際の裁判では、
引出権限の内容や発生原因事実について引出者側(被告)に説明をさせ、その後に、請求者側(原告)に反論をさせ、引出者側の説明に合理性があるか否かによって引出権限の存否を判断する
のだそうです。

たとえば、引出の際に、その引き出したお金が本人が病院に入るための医療費として必要であり、また入院期間中の本人の小遣いとして引き出されることになり、引き出すように依頼されたと被告が主張した場合には、そのような権限を授与するのは自然であり、特に原告からの反論が無い場合には、被告の引出権限を認定できるのでしょう。
訴訟の序盤戦では、このように、引出権限について具体的な主張の応酬がなされ、請求がそもそも認められるかが議論されることになります。
3 相手方が不正な引出行為をしたことを、どう証明するのか?
あなたが訴える側の場合、大前提として、出金を行ったのが被告であるということが認定されなければいけません。しかし、これがかなり大変なこともあります。
不正なお金の引き出しを指摘された被告は、大きく分けて以下の3種類の主張をすることが考えられます。
- 関与否認型(一切引出に関与していない、一部の引出のみにしか関与していない)
- 補助主張型(被相続人が引き出す際についていった、手伝っただけ)
- 本人交付型(引出自体は行ったものの、そのまま被相続人に渡した)
(1)関与否認型について
相手方が「お金の引き出しをしていない」もしくは、「一部しか引き出していない」と主張する場合です。この場合、被告の関与を裁判官に認めてもらうための証拠としては、以下のようなものが考えられます。
①取引履歴
被告の口座に、引き出した日またはそれと近いところで、引出金と似た金額の入金があるという取引履歴を証拠として提示できた場合、それは、被告が関与した可能性を強く推認させる有力な証拠となります。
もっとも、まずは被告の口座の特定を行う必要があるのですが、これは容易ではありません。また、引出金は、口座には入金されず、そのまま現金で保管されたり使われたりするケースがままありますので、なかなかこの証拠を提示することは難しいでしょう。

②伝票
払い出し伝票の筆跡が被告である場合にも、被告の関与が推認されます。もっとも、昨今はATMによる払い出しが大半ですから、払い出し伝票を使うことは少なくなっています。ただし、ATMの払い出しの場合でも、例えば被相続人と被告の居住地が遠く離れており、被告の居住地近くのATMが利用されている場合には、被告の引出が推認され得ます。
③被相続人の健康状態と通帳等の管理状況
被相続人の健康状態からして、物理的に払い出し場所まで行くことが困難な場合であり、かつ、被告が被相続人と同居などしており、通帳等を管理できる状況であった場合には、払い出し可能な状況であった被告による払い出しが推認され得ます。
(2)補助主張型について

相手方が、被相続人が引き出すのについて行っただけ、手伝っただけと主張することもあります。単に補助しただけであれば、被相続人の意思能力に問題がない限り、それは被相続人による引出行為であって、被告とは何ら関係ないことになります。
しかし、なぜわざわざ補助をしたのかという点は問題になります。この点については、被告の方から、当該引出行為が行われた経緯や、引出しされた現金の行方などについて主張する必要性があります。
(3)本人交付型について
相手方が、自分が引き出したということを認めたうえで、その引き出したお金を被相続人に渡したと主張する場合です。この場合、なぜそのようなことを行ったのかということを、被告側が主張立証すべきとされることが多いです。
具体的には、被相続人から払い戻しを依頼された経緯、そのお金の使い道などの可能な限りの詳細な事実関係と、これらを裏付ける証拠の提出が必要だとされています。
たとえば、被相続人が、ほとんど外出することもなく、現金を使う機会がないような生活を送っていたにもかかわらず、まとまった金額が頻繁に引き出されているとします。この場合、被告の主張内容が不自然であり、被相続人へ渡したとの事実が認められないとの結論になり得ます。
弁護士にご相談ください。
以上、細かく述べさせて頂きましたが、生前に引き出された預貯金をめぐる問題は、簡単そうに見えて意外に複雑です。相手方がすぐに認めて返金してくれるなら簡単なのですが、争われると立証をどうするか等、難しいです。よって、早期に弁護士にご相談を頂き、方針を打ち合わせて頂くのがよろしいかと存じます。

著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
関連項目
遺産分割についてさらに詳しく知りたい方はこちら
- 高額な土地がある場合の遺産の分割方法は?
- 愛人の子は遺産を相続できる?
- 遺産分割方法としての換価分割
- 亡くなった父親が再婚していた場合の遺産分割
- 共有物の管理に関する法改正(令和3年の民法改正)
- 遺産分割前に故人の預金を引き出してもいいの?
- 配偶者居住権とは
- 子供のいないご夫婦の相続
- 相続法改正!遺産分割前の預貯金の不正引き出し問題
- 被後見人が囲い込まれている場合の後見申立
- アパート経営者の遺産。賃料はどう扱う?
- 遠隔地で遺産分割調停が申し立てられた場合
- 遺産分割の「前提問題」とは?
- 遺産分割後に遺言が見つかった場合の対応
- 認知症の相続人がいる場合の遺産分割
- 遺産分割協議書のひな形
- 非嫡出子がいる場合の遺産分割
- 未成年者の相続人がいる場合の遺産分割
- 現物分割、代償分割、換価分割のメリット・デメリット
- 面識のない(知らない)相続人がいる場合の遺産分割
- 行方不明の相続人がいる場合、遺産分割はどうすればいいの?
- 生前に引き出された預貯金をめぐる訴訟の問題(引出の権限)
- 遺産分割協議と遺産分割協議書
- 遺産分割調停と審判
- 遺産に関連する訴訟について