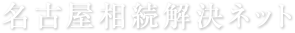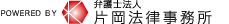相続問題についての知識
遺産分割協議書のひな形
遺産の分割方法について話し合いが完了した際には、後々トラブルが発生することを防ぐために、遺産分割協議書という書面を作成し、協議内容を書面化しておく必要があります。
遺産分割協議書の書式は、特に法律で決まっているわけではありませんので、以下、代償金の支払いがある事案の一般的なひな形をご紹介します。
なお、遺産分割協議書の内容は、それぞれの事案によって異なりますので、あくまでも参考としてご理解ください。
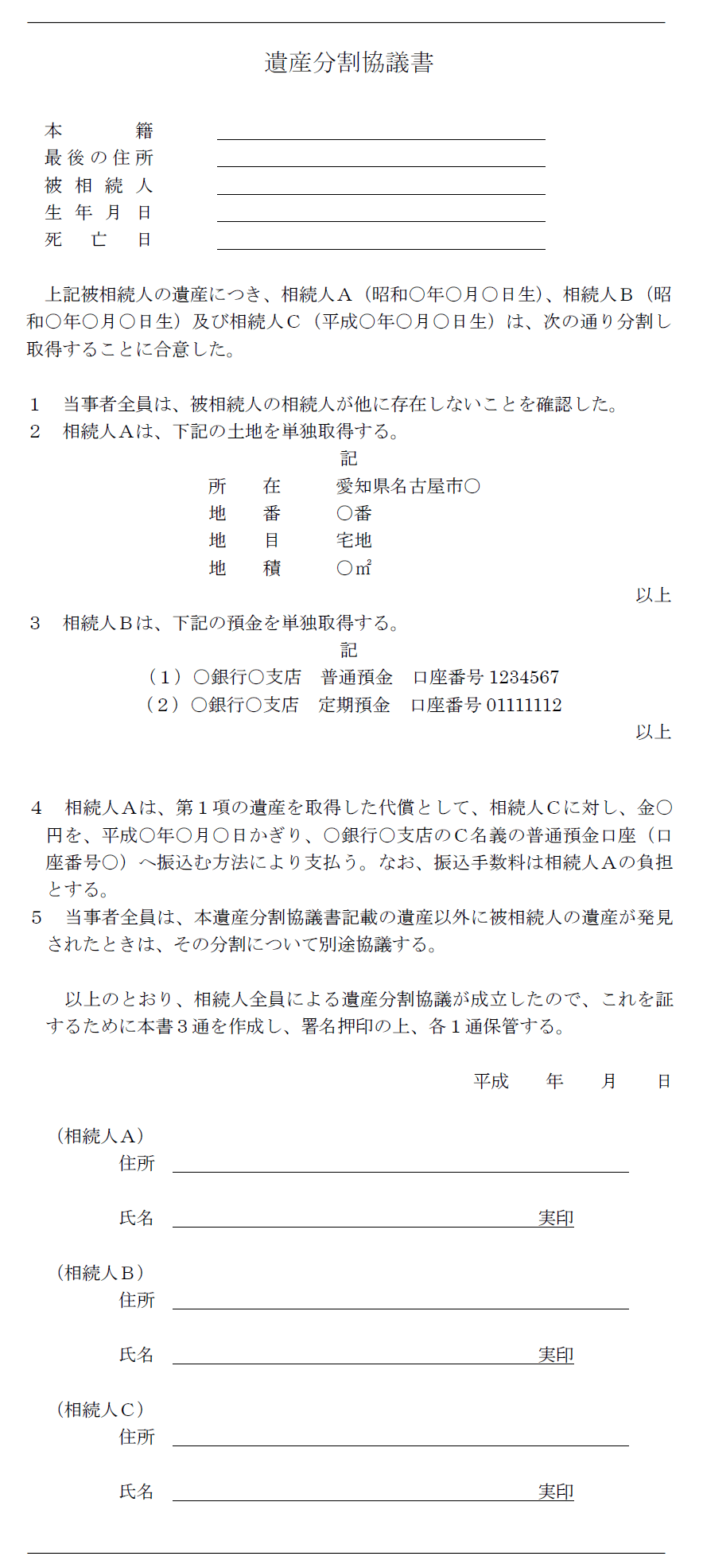
※1
不動産の場合、登記されている内容と協議書の記載に齟齬があると、相続登記に支障を来します。事前に相続登記手続を依頼する司法書士の先生等に確認していただくことをお勧めします。。
※2
預貯金は、対象が特定できるように正確に記載する必要があります。単に「○銀行の預金」のみでは不十分です。。
※3
各自の氏名は、後日のトラブルを防ぐためにも、自筆で記入しましょう。
また押印は、認め印ではなく、実印で行いましょう。
登記等の手続きの際に必要となりますので、遺産分割協議書には、各自の印鑑証明書を添付する必要があります。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
遺産分割についてさらに詳しく知りたい方はこちら
- 高額な土地がある場合の遺産の分割方法は?
- 愛人の子は遺産を相続できる?
- 遺産分割方法としての換価分割
- 亡くなった父親が再婚していた場合の遺産分割
- 共有物の管理に関する法改正(令和3年の民法改正)
- 遺産分割前に故人の預金を引き出してもいいの?
- 配偶者居住権とは
- 子供のいないご夫婦の相続
- 相続法改正!遺産分割前の預貯金の不正引き出し問題
- 被後見人が囲い込まれている場合の後見申立
- アパート経営者の遺産。賃料はどう扱う?
- 遠隔地で遺産分割調停が申し立てられた場合
- 遺産分割の「前提問題」とは?
- 遺産分割後に遺言が見つかった場合の対応
- 認知症の相続人がいる場合の遺産分割
- 遺産分割協議書のひな形
- 非嫡出子がいる場合の遺産分割
- 未成年者の相続人がいる場合の遺産分割
- 現物分割、代償分割、換価分割のメリット・デメリット
- 面識のない(知らない)相続人がいる場合の遺産分割
- 行方不明の相続人がいる場合、遺産分割はどうすればいいの?
- 生前に引き出された預貯金をめぐる訴訟の問題(引出の権限)
- 遺産分割協議と遺産分割協議書
- 遺産分割調停と審判
- 遺産に関連する訴訟について