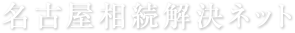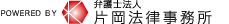アパート経営者の遺産。賃料はどう扱う?
アパート経営者の遺産。賃料はどう扱う?
被相続人がアパートやマンションなどの不動産を所有しており、第三者に賃貸している場合などには、毎月賃料が発生します。
被相続人が死亡したからといって、賃貸借契約が当然に終了することはありませんので、被相続人の死後も、賃料は発生し続けることになります。
この賃料は、誰が取得するのでしょうか?

賃料の取得者はだれ?
被相続人が死亡した後の賃貸借契約における賃貸人は、相続人全員のような状態になります。
そして、被相続人死亡後、遺産分割完了までの賃料について、誰がどのように取得するかは、最高裁で判断がなされています。
最高裁は、①遺産分割完了までの間の賃料債権は、遺産である不動産などとは別個の財産であり、各相続人が分割単独債権として確定的に取得する、②この点は、最終的に決定した遺産分割内容によって影響を受けない、と判断しています(最高裁平成17年9月8日判決)。
たとえば、相続人がA・Bの2人であり、各自の相続分が2分の1ずつである場合において、毎月賃料が20万円発生しているときには、A・Bそれぞれが、賃料を10万円ずつ取得することになります。遺産分割協議において、Bが賃貸不動産を取得することになったとしても、Aに対し、「被相続人死亡後、遺産分割完了までに発生した分の賃料を返せ」と請求することはできません。
複数の相続人がいる場合には、それぞれが賃料を取得する権利を有することになりますので、賃料の受領方法(賃借人から各相続人に対して賃料を支払ってもらうのか、相続人の代表者に対して支払ってもらうのか)や、賃貸不動産の管理方法(誰が管理するのか、管理費用をどこから支出するのか)などを協議して決める必要があります。
なお、遺産分割が終了した後の賃料は、遺産分割でその賃貸不動産を取得することになった人が取得することになります。
ひとり占めされた賃料を取り戻す方法
以上のように、本来は相続人間で賃料を分けなければいけませんが、実際には、特定の相続人が単独で賃料全額を受領していることがあります。このような場合には、原則として、地方裁判所において、その相続人に対して、賃料の返還を求める民事訴訟を提起することとなります。
他方で、遺産分割については、話し合いができない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。
したがって、賃料の返還を求める手続きと、遺産分割内容を決める手続きを別々の裁判所で行わなければならず、とても大変です。
ただし、相続人間で、賃料について、遺産分割調停において話し合う対象に含めることを合意した場合には、調停手続において、遺産の分け方と一緒に、賃料についても協議して取得内容を決定することも可能です。
まとめ
賃貸不動産がある場合には、決めるべき事項が多くなり、負担が大きくなります。確実に賃料を取得するために、早期対応が必要不可欠ですので、お早めに弁護士にご相談ください。
著作責任者プロフィール

弁護士 片岡 憲明
弁護士法人 片岡法律事務所 代表
愛知県弁護士会所属 登録年(平成15年)
1977年岐阜県大垣市生まれ。東京大学法学部卒業、2001年司法試験合格。2003年より弁護士登録し、名古屋市を拠点に法律実務に従事。現在は、弁護士法人片岡法律事務所に所属。
特に、相続・離婚などの家事事件や、労働問題・特許訴訟など企業法務に強みを持ちます。
愛知県弁護士会および日弁連の各種委員会にも長年にわたり参加し、司法制度や法的実務の発展にも尽力。
依頼者の方に少しでも有利な主張はできないかを検討し、最大限に証拠を集め、相手方に対し、説得力のある主張をし、解決に導きます。
遺産分割についてさらに詳しく知りたい方はこちら
- 高額な土地がある場合の遺産の分割方法は?
- 愛人の子は遺産を相続できる?
- 遺産分割方法としての換価分割
- 亡くなった父親が再婚していた場合の遺産分割
- 共有物の管理に関する法改正(令和3年の民法改正)
- 遺産分割前に故人の預金を引き出してもいいの?
- 配偶者居住権とは
- 子供のいないご夫婦の相続
- 相続法改正!遺産分割前の預貯金の不正引き出し問題
- 被後見人が囲い込まれている場合の後見申立
- アパート経営者の遺産。賃料はどう扱う?
- 遠隔地で遺産分割調停が申し立てられた場合
- 遺産分割の「前提問題」とは?
- 遺産分割後に遺言が見つかった場合の対応
- 認知症の相続人がいる場合の遺産分割
- 遺産分割協議書のひな形
- 非嫡出子がいる場合の遺産分割
- 未成年者の相続人がいる場合の遺産分割
- 現物分割、代償分割、換価分割のメリット・デメリット
- 面識のない(知らない)相続人がいる場合の遺産分割
- 行方不明の相続人がいる場合、遺産分割はどうすればいいの?
- 生前に引き出された預貯金をめぐる訴訟の問題(引出の権限)
- 遺産分割協議と遺産分割協議書
- 遺産分割調停と審判
- 遺産に関連する訴訟について