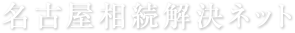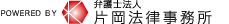依頼者:被相続人の妻(60代)
相手方:被相続人の兄弟姉妹
被相続人の遺産は、不動産、預貯金、株式であり、不動産については共有名義のものがあるため、誰が何を取得するかで争いが生じました。
また、不動産の価格についても意見の相違があったため、その調整も必要な事案でした。
問題点
以下の3つの問題点がありました。
①誰がどの遺産を取得するか。
②不動産の価格をどうするか。
③共有名義の不動産をどのように処理するか。
解決内容
相手方が遺産分割調停を申し立てたため、調停手続の中で、①~③の問題点について話し合いがなされました。
その結果、
①「誰がどの遺産を取得するか。」については、相続人間で歩み寄りをすることができたため、基本的には各々が希望する遺産を取得することができました。
②「不動産の価格をどうするか。」についても、鑑定を実施するかどうかも検討されたのですが、最終的には話し合いにより妥結点を見つけることができました。
③「共有名義の不動産をどのように処理するか。」については、不動産業者に売却を依頼し、持分に応じて売却代金を振り分けるということで解決を図ることができました。