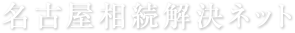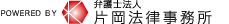依頼者:長女、次女、長男(40代~50代)
相手方:女性(70代)
被相続人(依頼者らの父)は、依頼者らが幼少の頃に、多額の借金を背負い、家出をしており、それきり依頼者らの前に現れることはありませんでした。
ところが、被相続人の生前、被相続人と生活していたという女性から、依頼者らに対し、被相続人の預貯金等の相続手続を行って欲しい旨の通知があり、依頼者らは被相続人の死亡を知りました。
依頼者らは、被相続人が、多額の借金を背負い家出をしたとの認識であったため、相続放棄をするべきか、また、相手方とどのように話を進めればよいか不安に思われ、当事務所にいらっしゃいました。
問題点
依頼者らは、被相続人の遺産(主に預貯金)を一旦相続して、解約手続を行い、解約金全額を相手方女性に渡す方向で検討されていました。
もっとも、被相続人が多額の負債を負っていれば、この負債をも相続することになってしまいますので、解約手続を進める前に、早急に相続放棄するか否かを判断する必要がありました。
この、相続放棄するか否かの判断にあたり、被相続人の負債状況を調査する必要がありましたが、被相続人の負債の有無は、主に長年被相続人と同居していた相手方女性より聴き取るほかありませんでした。
解決内容
まずは、相手方より伺った、被相続人の生前の生活状況、及び、かつて被相続人が所有していた不動産に設定された抵当権が抹消されていることから、かつて被相続人が負っていた負債が完済されている可能性が極めて高いと判断し、相続放棄をしないことを決断されました。
続いて、相手方との間で、合意書を交わし、解約した被相続人の預金を相手方に支払い、解決となりました。